大柴胡湯について
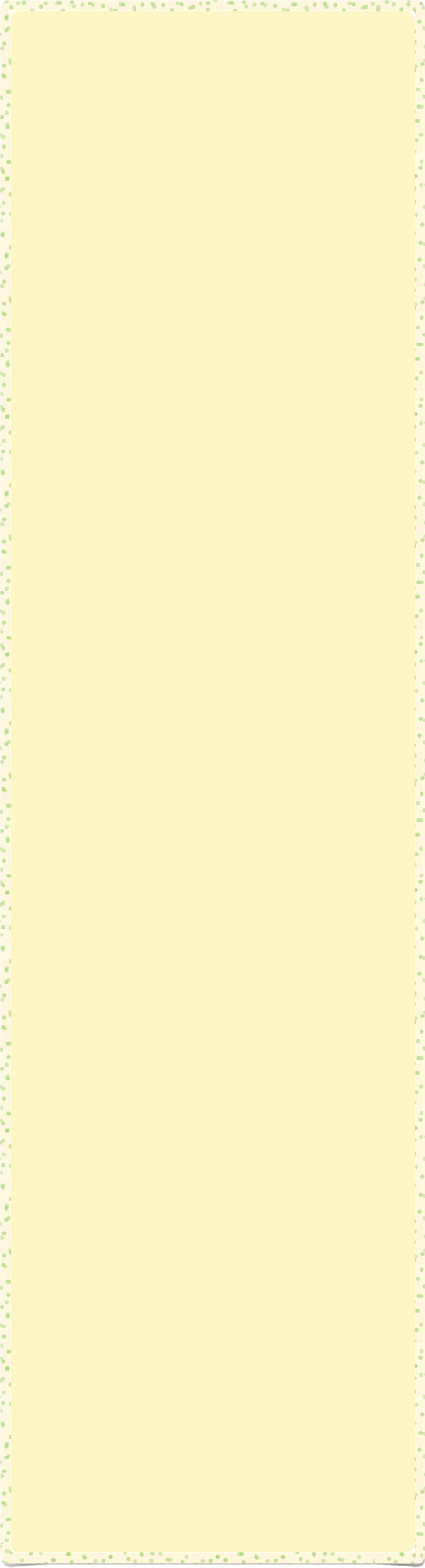

大柴胡湯について
(平成27年7月26日)
今回は大柴胡湯(だいさいことう)について、少し専門的なことを整理した。
大柴胡湯は、傷寒論では発熱、悪寒、頭痛の症状を呈する「太陽病」、すなわち、風邪の初期から少し進んで食欲がなくなり、往来寒熱つまり悪寒と発熱を繰り返し、吐き気が起こる「少陽病」の時期を経て、更にもう少し進んで、持続的な発熱及び便秘をともなう「陽明病」になろうとする手前の時期に使う処方とされている。つまり往来感熱、悪寒と発熱を繰り返しながら、食欲がなくて、吐き気がして、みぞおちがつまった感じがして便秘するというときに使う処方である。
ところが最近の外来でこのような状態でみえる患者さんはめったにおられない。もっぱら慢性疾患に使う。がっちりした体格で、腹診で心下部の強い緊張に、胸脇苦満を伴う条件を備えているときに使うということになっている。そのような所見を具える人は高血圧、肥満、肩こりなどの人に多い。
人体はストレスにさらされ緊張すると交感神経が興奮する。それに伴って筋肉も緊張し、肩こり、首こりなどの身体症状が起こり、イライラ、怒り、不安などの精神症状が出てくる。そのときに腹を診ると「胸脇苦満」という、右季肋部を中心に肋骨の下よりの方向へ指をそろえて押し込んだ時の微妙な不快感を確認でき、これが柴胡剤の基本的な腹診所見となっている。ストレスに伴う心下部から肋骨弓の上下に跨る不快感を「肝気鬱結」と呼んでいる。そしてその程度によって柴胡・黄芩が組み合わされたいわゆる柴胡剤の種類を決めるのである。大柴胡湯はその「胸脇苦満」の程度の最も強い状態に使うことになっている。
そこでストレスの身体の全身に及ぼす影響を生理学的に整理してみる。
交感神経の興奮は、中枢神経では特に大脳辺縁系の情動の部分には不安、怒り、恐れなど神経過敏な七情の症状として表現される。呼吸器系では気管支の痙攣となって喘息発作と表現されるが、それは喘息の患者に見られ、普通の人にはあまりみられない。循環器系では心臓の興奮となって強い動悸として表現される。消化管では蠕動運動の異常により、喉やみぞおちの痞え、悪心、嘔吐、腹痛、下痢として表現される。泌尿生殖器系では膀胱炎のような不快感や頻尿、尿管結石による尿管の痙攣発作が起こるかも知れない。性機能でインポになるかもしれない、また上腹部には胆嚢や、膵臓が胆管、膵管が十二指腸とつながるファーター乳頭部分にある括約筋の痙攣発作となることもある。その時「胸脇苦満」があると柴胡剤のどれが良いか症状に応じて選択するのである。
大柴胡湯の場合は内臓平滑筋のけいれん発作を伴う場合に良いとされている。それには大柴胡湯の中の芍薬、甘草、枳実という生薬の組み合わせが、筋肉のけいれんを緩め、消化管の運動を正常にするとされている。上腹部で内臓の筋肉平滑筋が痙攣するよう病気は少なくない、食道アカラシア、食道けいれん、胃痙攣、幽門痙攣、胆石発作、胆道ジスキネジー、膵炎、尿管結石発作などである。しかし当院外来でそのような激しい症状の人は見ることはほとんどなく、よく見えるのは先に述べた、体格の良い人の高血圧や、不安、不眠、上腹部の不快感、便秘、下痢などの症状に大柴胡湯を処方することなる。時にストレスで起こる円形脱毛の人に大柴胡湯を処方することもある。
ちなみに心臓の動悸の症状が強いときは竜骨・牡蠣を加えた柴胡加竜骨牡蠣湯(さいこかりゅうこつぼれいとう)ということになる。喉のつかえが強い場合には半夏厚朴湯(はんげこうぼくとう)を併せる。すなわち柴胡剤でもストレスに対する反応の微妙な違いによってバリエーションがあり、そのあたりを的確に区別できる事が臨床のコツとなっている。
大柴胡湯はストレスで消化管や泌尿器の平滑筋の痙攣による、痞えた症状が強いときの処方であった。
そしてストレスによる神経過敏が消化管の症状を伴う事を漢方では「肝気横逆」、或いは「肝脾不和」と呼び、大柴胡湯もその病態に対応した処方であった。
